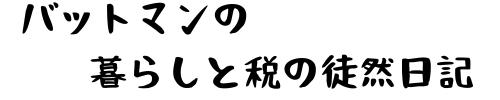自民党総裁選やその後の与野党協議に向けて、「給付付き税額控除」が再び注目されています。
これは、消費税率引上げに伴う低所得者対策の一つとして議論されていた制度です。
※「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)」第7条第1号イ及びロ
結果として導入されたのは「軽減税率」でしたが、昨今の物価高対策や低所得者対策の一つとして検討されているようです。
個人的には、給付付き税額控除には一定の合理性とメリットを感じています。しかしながら、制度の公平性を担保するためには、何よりも「所得の正確な把握」が不可欠です。
現状では、分離課税の所得や副業収入など把握が難しい所得が存在します。これらを含めた所得の全体像を正確に捉えるためには、マイナンバーの活用が前提となると思われます。
一方で、金融所得など政策的に累進課税を避けるべき領域も(ここは議論が分かれますが)あります。分離課税の意義を尊重しつつも、給付付き税額控除の執行においては、これらの所得(税額)も加味して、制度の整合性と公平性を両立できるのようにすべきではないかと考えます。
税制は常に「公平」「簡素」「中立」の三原則の間で揺れ動きます。給付付税額控除の導入にあたっては、制度設計の精緻さだけでなく、国民の理解と納得を得るための丁寧な説明が求められます。
給付付き税額控除以前の問題として、国民保険料の算定や自治体による各種措置の対象基準(所得)には、分離課税の所得が反映されていないという課題もありますが・・・
給付付き税額控除の議論に思う──公平性と所得把握の課題
 消費税
消費税